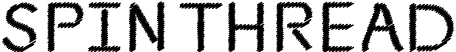その契約大丈夫? | 実話をもとにホームページ制作における契約の注意点を解説
今回は実際に当社に相談があった事例をもとに、ホームページ制作を進める際の契約において気をつけていただきたいと感じたことをお伝えします。
※契約期間など一部の数字を変更しいます(変更していますが、事実に限りなく近くしています)
[ 目次 ]
異常に長い契約期間
実際に当社へ相談してきた企業さまがとあるWeb制作会社と交わした契約は、保守管理契約として102ヶ月(8年半)というとんでもなく長い契約期間が結ばれていました。この業界に携わって12年経ちますが、こんなに長い期間の縛りがある契約は聞いたことがありません。
契約期間が設定されている契約ももちろんありあすが、よくあるパターンとしは初期費用0円、もしくは5万円などの低額でホームページを作成し、公開後に月額費用を毎月請求するパターンです。このようなパターンにおける月額費用はWeb制作会社によって異なりますが、5,000〜10,000円くらいが多いと思います。
このパターンはおそらく制作時点では赤字となり、公開後の月額費用を積み上げることで赤字を解消し、損益分岐点を上回ったあとは売上がほぼ粗利益となっていくビジネスモデルです。この記事ではここから先便宜上「サブスク型ホームページ制作」と呼ぶことにします。
サブスク型ホームページ制作は赤字からスタートするためWeb制作会社側としては公開後すぐの解約は避さけなければなりません。そのため最低契約期間を数ヶ月〜1年としているケースが多く見受けられますが、この数字からみても102か月というのがいかに異常な数字かが分かります。(ちなみに相談事例の場合は通常の月額費用が税込11,000円、102か月の契約期間中は特別値引き価格として6,259円という契約でした)
お客さま側からすると初期費用を抑えられ毎月の月額費用も決して支払えない価格ではないので採用しやく、Web制作会社としては契約件数を伸ばしやすいのだと思われます。つまり数で勝負するモデルとなり、サービスを提供するWeb制作会社側としては契約者数を伸ばせば伸ばすほど、月額費用が積み重なり安定した収益を得られるようになるのがメリットです。
ではご相談事例の制作費はどうかというと、別途200万円近くの金額を支払う契約が結ばれています。この制作費は分割払いも選択できるようになっているのですが、この制作費も102ヶ月での分割となっていて、保守管理と全く同じ契約期間になっています。
先述したサブスク型ホームページ制作のパターンとは明らかに異なり、しっかり制作費を支払った上で、さらに異常に長い保守契約期間でお客さまを縛っているというかなり特殊な契約でした。
もし契約期間がある場合は、契約期間は何か月(何年)か?また制作費は別途かかるのか?かかるとしたらいくらか?をしっかり把握していただければと思います。
その期間や費用が妥当かどうか全く検討がつかない場合は、周りにいるWebに詳しい方、自社の周りにそのような方がいないのであれば、例えば取引先のWeb担当者、もしくは取引先のホームページを作成したWeb制作会社を教えてもらい確認するなど、方法は何でも良いのでWeb業界のことに理解がある方に確認することを怠らないでください。
契約が終了するとホームページが消える
相談事例では管理画面からホームページをお客さま側で更新できるようWeb制作会社独自のCMS(コンテンツマネージメントシステムの略。Webの専門知識がない方でもホームページを更新できる仕組み)が導入されており、専用の管理画面からお客さまが自由にいつでも更新できる仕組みとなっていました。
解約した場合はこのCMSの管理画面が使えなくなり、さらにホームページ自体も消える内容の契約でしたが、この内容自体はサブスク型ホームページ制作でも一般的な内容です。
しかしながら、相談事例では安くない制作費を支払っているにも関わらず、ホームページまで消されてしまうのは他のサブスク型ホームページ制作とは事情が大きく異なると当社では考えています。
公開後も契約が続くようなケースの場合、解約したら制作したホームページはどのようになるのか、必ず確認することをオススメします。
ドメインもWeb制作会社が管理している
この相談事例ではドメインもサーバーもWeb制作会社が管理しており、解約すると今まで使用していたドメインは一切使えないという契約でした。全てではないかもしれないですが、サブスク型ホームページ制作ではホームページが消えても、(ドメインの移管作業などが発生し費用がかかる可能性がありますが)ドメインに関しては基本的には引き続き今までのドメインを使用できるようになっています。
200万円近くの制作費は別途支払う上に保守契約期間が102ヶ月もある、さらに解約するとホームページが消えるだけでなく、ドメインも使用できなくなる内容でかなり悪質だと考えられます。
ドメインはできれば自社で契約・管理した方がよいものですが、Webに関して知識がない方からするとよく分からずとっつきにくいものだとも思います。そのようなことから制作してもらったWeb制作会社など外部パートナーに契約や管理をお任せすることもあるかもしれません。
しかし、そのような場合でも何らかの事情で将来別の外部パートナーに管理をお願いする可能性はゼロではないことから、管理契約をストップした場合にドメインを引き続き使用することができるかどうかは、必ず事前に確認するようにしてください。
仮にドメイン移管という作業が発生し手数料がかかると言われても(手数料は必ず確認してください)、基本的には了承すべきだと考えます。ドメインが変われば名刺やパンフレット、場合によっては看板など、さまざまなものを変更しなければならなくなりますし、それ以上に運用し続けて積み重ねたドメインのパワーを手放すことになるからです。
ホームページの運用期間が長ければ長いほど、基本的には使用しているドメインは評価されていきますが、新しいドメインに変更することはそれまで積み上げたドメインの評価を自ら手放すことになります。ドメインのパワーは検索結果の上位表示などに関係すると言われているため、新しいドメインに変えることはSEO的に不利になるとを意味します。
そのようなことを踏まえると、外部パートナーにドメイン管理をお任せしている場合、ドメイン移管で手数料がかかることになっても、今までのドメインを使用すべきだと当社では考えています。
制作はA社、保守管理はB社など契約が複雑
この相談事例では契約に関して2社が絡んでいて、お客さまからすると非常にわかりにくい複雑な構造になっていました。私もお客さまから相談を受けた際、当初はお客さまの言っていることがよく理解できませんでした。
しかしながら、お客さまが手元に保管されていたしおりを確認したり、契約した企業のホームページを調べることでようやく全容を理解することができました。わかったことはB社独自のCMSを搭載したホームページを、販売代理店としてA社が売っていたことがわかりました。
そのようなことから制作に関してはA社、公開後の保守契約はB社との契約という、お客さまからすると理解が難しいものになっていました。通常は制作したWeb制作会社が公開後の保守管理を行う形が多く契約が複数社に分かれることはないので、お客さまからすると理解することが難しく、不本意にもよく分からないまま契約してしまったということでした。
契約が複雑で分からないようであれば、理解するまで聞いてみましょう。こういったことに丁寧に対応してくれるかどうかで、その企業の姿勢が垣間見えます。そのようなことからも、契約前に長くお付き合い出来る企業かどうかを見定める良い機会と捉え納得するまで確認することをおすすめします。
最後に。こんなWeb制作会社は要注意!
お客さま側からの連絡は常に折り返し
この相談事例では、Web制作会社側にはサポートセンターがあり、公開後は基本的にそちらに連絡することになっていました。相談を受けた企業のご担当者さま曰く、サポートセンターはあくまでも用件を受ける一次対応でその場で回答することはなく、常に折り返しの連絡とのことでした。一度だけ私がご担当者さまの知人という体でサポートセンターへ連絡をしたことがありますが、やはり同じように折り返しの連絡となりました。
折り返しの連絡となるといつかかってくるかわからないですし、かかってきた時に電話を受けられないといったことも予想されます。このようなことからお客さま側としてストレスが大きいものです。
少なくても契約後の問い合わせに関しては出来る限り、少ない回数で解決したいものです。折り返しするすべての企業は避けるべきというつもりはありませんが、いろんなところで不信感を持った中で、問い合わせもこのような対応だと企業としての姿勢自体を疑わざるを得ません。
このようなポイントも一つの判断基準としてもっていただくと良いと思います。
要望に対して真剣に向き合わない
ご相談いただいた企業のご担当者さまは、より良いホームページにしようといくつか要望を伝えたようなのですが、取り合ってもらえずさまざまな理由をつけては要望を取り入れてくれなかったとおっしゃっていました。
確かにWeb制作の現場に長くいると、明らかに成果から遠ざかってしまうような要望をお客さまからいただくことはあります。しかし、その場合でも単に否定するのではなく、お客さまの知識レベルに合わせた言葉を選びながら、要望を行うことでのデメリットを丁寧な説明をすることは必須だと思います。さらに可能であれば代替え案を提示するなど、お客さま側に立って考えることが求められます。
このようなやり取りでも企業としての姿勢が垣間見得ますし、相性なども確認することができます。契約前にこれらをすべて把握するのは難しいですが、出来る限り一つ一つのやり取りに関してこれから長く付き合っていけそうな会社かどうか見極めることを意識していただくと良いと考えています。
他にもたくさんありますが、この相談事例に関係する注意点について最後に少し書かせていただきました。これとは逆の視点でWeb制作会社の選び方についても別記事で詳しく書いていますので、合わせてご確認いただければと思います。
Web制作会社の選び方については知りたい方は…
この相談事例のような悪質なWeb会社と取引することがないよう、Web制作会社の選び方については別記事「Web制作会社の選び方」で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。
まとめ
この相談事例のケースでは契約内容、契約の複雑さ、連絡方法などどれをとっても顧客側の立場に立っているとは到底思えず、どれも自社都合ばかりであると同じ業界に属するものとして強い憤りを感じました。
相談いただいた企業のご担当者さまは、「制作段階ですでに販売店とWeb制作会社の2社には不信感しかなく、関係はこじれてしまっていた」とのことでしたが、もし仮に制作段階では問題なく無事公開できていたとしても、公開後長く信頼関係を構築しながら運用していくのは難しかっただろうと推測します。
少しでも疑問点があれば質問を投げかける。そしてその回答への対応、また的を得た回答かどうか、長く安心して取引を続けられるWeb制作会社かどうかを見極めるためにも、特に契約前は注意深く観察することが重要です。
このような悪質なWeb制作会社への契約がなくなるよう、Web業界に携わる身として出来ることを行なっていきたいと思います。
「日々の仕事」ブログでは、ホームページ制作の現場において実際の出来事や気づきなどのお役立ち情報を発信していますので、ぜひ他の「日々の仕事」も合わせてご覧ください。
他の「日々の仕事」はこちら
よく読まれる記事
-
日々の仕事
サーバーの変更(移管)に伴うメール移行 | 正しい移行手順と注意点
長くホームページを運用していると、何らかの事情でホームページを引っ越し(新しいサーバーへ変更)するということが出てきます。例えばサーバー管理をお願いしている現在のWeb制作会社の対応に不満があるから、別の新しいWeb制作…
詳細を見る
-
日々の仕事
ホームページの更新や修正を新しいWeb制作会社へ依頼する時に気をつける7つのこと
「他社で作ったホームページの更新や修正をお願いすることは出来ますか?」という質問を実はよく受けます。この質問をよく受けるということは、そもそも出来ないと思っている方が相当数いるのでは?と感じているのですが、この記事を読ん…
詳細を見る
-
日々の仕事
ホームページの制作費用を支払うタイミングは? | 一般的な支払い時期と方法についてポイントを解説
ホームページの作成を外部のWeb制作会社に依頼する際の費用について、先日ブログを書きました。 ホームページ制作の費用について詳しく知りたい方はこちら・・・「ホームページの制作費用はどのくらいかかる? | より正確な費用を…
詳細を見る
-
日々の仕事
ポップアップ広告を表示するタイミング | ユーザ視点から注意点を探る
検索結果一覧などから気になるホームページへ遷移した瞬間、もしくはページ遷移した瞬間にコンテンツを覆い尽くして表示されるポップアップ広告。多くのユーザにとって「鬱陶しい」と不快に感じさせる手法に対し、Googleは2017…
詳細を見る
-
日々の仕事
Web制作会社に対する不満 | 具体的な5つの不満を挙げてWeb制作会社の見極め方を解説
今この記事を読んでくださっている方は、専任のWeb担当者であったり、本業をかかえながらWeb担当者を兼任している方、他のスタッフの方より少しITが詳しいだけでWeb担当者を無理やり押し付けられた方など、いろんな方がいるの…
詳細を見る
-
日々の仕事
ホームページ制作に関する不安や悩み(第7回)| Webデザインのイメージをうまく伝えられるだろうか?
10年以上Web業界に携わってきた中で、ホームページに対するクライアントの不安や悩みに関する多くの声に触れ、クライアントがどのようなことに不安や悩みを持つのか傾向を掴んできました。そういった実際の声を改めて拾い集め、クラ…
詳細を見る